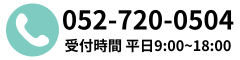再生可能エネルギー(再エネ)の導入を促進するため、日本では「FIT制度」と「FIP制度」という制度が採用されています。
この2つはいずれも、再エネを利用して発電した電気を売電するための制度です。しかし、どこが違うのかよく分からない方もいるでしょう。
このコラムでは、「FIT制度」と「FIP制度」の概要と違いについて解説します。再エネを活用した売電に興味がある方は、ぜひ参考にしてください。
🌿 省エネ診断
5つの質問で、あなたに最適な
省エネ対策をオススメします!
診断結果
📚 関連記事をチェック
FIT制度・FIP制度とは?

二酸化炭素排出量の抑制や、エネルギー自給率のアップを目的として、再エネを普及させる必要性が高まっています。
日本の2020年度の発電電力量のうち、再生可能エネルギーが占める割合は約20%でした。国は、これを2030年度までに36~38%程度まで引き上げることを目指しています。
日本では再エネの普及を目指し、2012年に「FIT制度」、2022年に「FIP制度」という制度が採用されました。
この2つの制度は、「太陽光」「風力」「水力」「地熱」 「バイオマス」の5つのいずれかの再エネを利用して、国が定める要件を満たす事業計画に基づいて発電した電気を、国が買い取るというものです。
ここでは「FIT制度」と「FIP制度」の概要を解説します。
引用:資源エネルギー庁「再生可能エネルギー – FIT・FIP制度 ガイドブック」
FIT制度
FIT制度(Feed-in Tariff/再生可能エネルギーの固定価格買取制度)とは、再エネで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度です。
日本はエネルギー自給率の低さが課題となっていたことから、再エネの普及を促進するため、2012年にFIT制度が開始されました。
この制度では、電力会社が電気を買い取るための費用の一部を、「再エネ賦課金」という形で電気料金に上乗せして国民から集めています。
FIP制度
2012年に始まったFIT制度ですが、いくつかの課題がありました。
まず、国民から集める「再エネ賦課金」の負担が大きいという点です。この再エネ賦課金は年々増加傾向にあり、国民への負担増が懸念されていました。
また、固定価格で買取を行うFIT制度は、火力など他の電力市場から切り離されたものでした。しかし、今後さらに再エネを普及させるためには、他の電力市場と統合させる必要があったのです。
こうしたFIT制度の課題に対応するため、2022年にFIP (Feed-in Premium)制度が開始されました。FIP制度は、再エネによって発電した電気を市場価格に基づいて売電する「市場連動型」のシステムです。市場の変動によって、売電収入も変わってきます。
FIP制度では、電気を売った価格に「プレミアム」と呼ばれる補助額が上乗せして交付されます。プレミアムの金額は、あらかじめ設定された基準価格(FIP価格)と参照価格(市場取引などで期待される収入)の差額によって決まり、1ヶ月ごとに更新されます。
FIT制度とFIP制度の買取価格の違いは、以下の図をイメージすると分かりやすいでしょう。 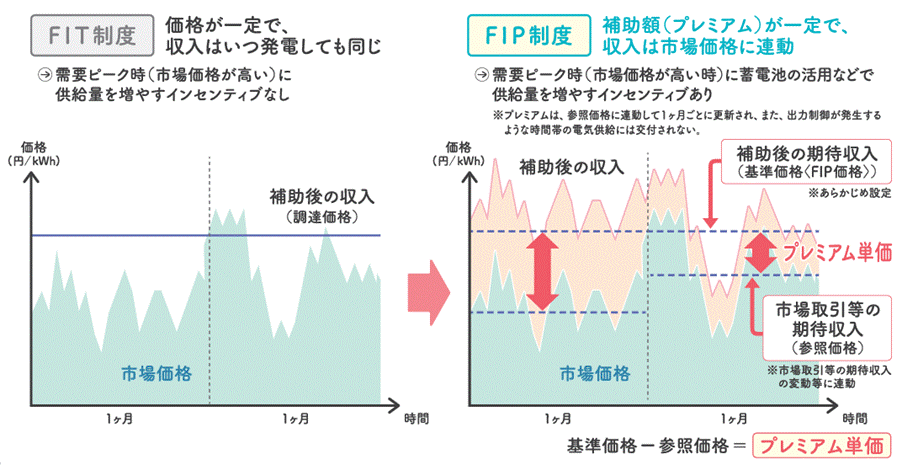
画像引用元:資源エネルギー庁「再生可能エネルギー – FIT・FIP制度 ガイドブック」
また、FIT制度にはないFIP制度の特徴として、「計画値」を算出しなければならない点があげられます。
計画値とは、再エネで発電できる電力量の見込みのことで、実際に発電した「実績値」と一致させる必要があります。この業務は「バランシング」と呼ばれます。
計画値と実績値が一致しない場合(インバランス)、その差を埋めるためのペナルティを支払わなければなりません。
ただし、事業者がペナルティを全て負担することは難しいため、プレミアムの一部に「バランシングコスト」が加算されて交付されます。

FIT制度とFIP制度のメリット・デメリット

FIT制度とFIP制度の仕組みを踏まえ、2つの制度のメリット・デメリットをそれぞれ見ていきましょう。
FIT制度のメリット
FIT制度の主なメリットは売電収入が安定していることです。FIT制度の買取価格は一定のため、契約期間中は安定した収入を得られます。
例えば、自宅で再エネによる売電を始める場合、太陽光発電パネルや蓄電池の設置コストがかかります。FIT制度なら一定期間に安定した収入が得られるため、初期投資の回収や収益の計画を立てやすいでしょう。
FIP制度のメリット
FIP制度の主なメリットはより多くの売電収入を得られるチャンスがあることです。
FIP制度では、市場価格に基づいて電気を売ることができます。何らかの理由で電力需要が高まった時や、再エネ以外のエネルギー資源が高騰した時などは、高額での売電が期待できます。
さらに、FIP制度による取引では「プレミアム」が加算されるため、FIT制度と比べて多くの収益を得られる可能性が高いでしょう。
FIT制度のデメリット
FIT制度の主なデメリットとして、収益性を上げにくいことや再エネ賦課金の負担があることがあげられます。
FIP制度では市場価格に基づいて売電できるため、タイミングによっては高額で売電することも可能です。しかし一定価格で売電するFIT制度では、電気の市場価格が上がってもその恩恵を受けられません。
またFIT制度は、国民から集められる再エネ賦課金を活用しています。再エネ賦課金は電気代に上乗せされるため、賦課金が上がると電気代が高くなり、国民全体の負担が重くなってしまうでしょう。
FIP制度のデメリット
FIP制度の主なデメリットは、収益が不安定なことやペナルティのリスクがあることです。
FIP制度は市場価格に連動した価格で売電する制度のため、市場価格が落ち込めば売電収入も下がってしまいます。また、市場の変動によってプレミアムの価格も下落する時期があるため、あまりプレミアムの付加価値を得られないケースもあるでしょう。
さらにFIP制度の利用者は、計画値と実績値が一致しない場合に支払うペナルティを考慮しなければなりません。
しかし、太陽光発電などは天候など自然の影響をダイレクトに受けるため、天候の悪い日が続けば思ったように発電できないこともあります。こうしたやむを得ない理由であっても、FIP制度ではペナルティが課されてしまいます。
FIT制度とFIP制度、どちらがお得?

ここまでFIT制度とFIP制度の違いを見てきましたが、「結局どっちがお得なの?」と思うでしょう。FIT制度とFIP制度、どちらの買取価格が高くなるかは市場の状況によって左右されるため、どちらがお得と明言することはできないのです。
FIT制度とFIP制度には、それぞれメリット・デメリットが存在します。FIT制度では安定した収入を得ることができますが、市場価格が上がっても売電収入は上がりません。FIP制度では、市場価格が上がれば収益も上がるものの、収益が不安定でペナルティのリスクもあります。
どのように売電収入を得たいか、どちらがご自身の事業計画に合っているかによって選びましょう。

まとめ

FIT制度とFIP制度は、どちらも再エネで発電した電気を売るための制度で、今後再エネの普及を目指すためには不可欠なものといえます。
FIT制度とFIP制度は似ていますが、「FIT制度は固定価格での買取」「FIP制度は市場価格に基づく買取」という大きな違いがあります。思い描く事業計画によって、どちらを選ぶか決定しましょう。
FIT制度とFIP制度に興味があり太陽光発電システムや蓄電池を設置したい方は、エコまるにご依頼ください!まずは資料請求・お見積もりから!