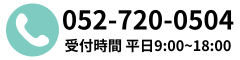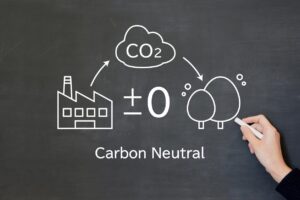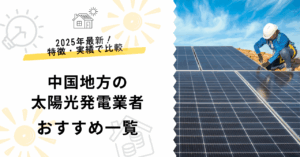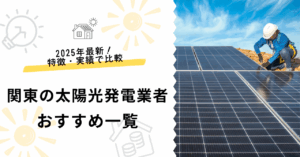再生可能エネルギーの普及が進む中で、発電した電力をどのように活用するかが、企業のエネルギー戦略において重要なテーマとなっています。
太陽光や風力などで発電した電気を、離れた拠点でも有効に使いたいというニーズに応える仕組みが「自己託送」です。自社で発電した電力を効果的に活用することで、電気料金を大幅に削減し、脱炭素化に寄与できる取り組みです。
本コラムでは、自己託送の仕組みから料金体系、そして導入によるメリット・デメリットまでをわかりやすく解説します。企業の電力活用を見直す一つの選択肢として、ぜひご一読ください。
🌿 省エネ診断
5つの質問で、あなたに最適な
省エネ対策をオススメします!
診断結果
📚 関連記事をチェック
自己託送とは

自己託送とは、遠隔地にある自社の発電設備で作った電力を、自社の別の拠点で使用することです。詳しい定義や仕組みと流れ、一般的な電力供給との違いを解説します。
自己託送の定義と概要
自己託送は、自社の発電設備所で発電した電力を、電線など電力会社の送配電網を利用して、自社の他の施設へ送電することです。
太陽光発電システムなど、再生可能エネルギーを活用した発電所で作った電力を、需要のある事業所や工場に供給します。これにより、電力の自給自足やコスト削減、環境負荷の低減が期待できます。
従来、自家用発電設備を導入する場合は、消費地点と同一敷地内に設置する必要がありました。しかし2013年に自己託送が制度化されたことにより、発電所と消費地点が離れていても、電力を移送できるようになりました。
2011年の東日本大震災で電力がひっ迫したことをきっかけに、余剰電力を有効活用し安定共有を図る重要性が高まったことと、再生可能エネルギーを活用した発電設備の導入普及を目的として可能になった制度です。
自己託送の仕組みと流れ
自己託送では、自社が所有する発電設備で発電した電力を、電力会社の送配電網を介して、自社の他の拠点に送ります。
自己託送には、事業者コードの取得と、託送供給契約・発電量調整供給契約の締結が必要です。
流れは、まず発電設備で発電した電力を送配電網に送り込みます。そして、消費地点では、その送られてきた電力を受け取って使用します。
この過程で、託送料金と呼ばれる送配電網の使用料を支払います。また、発電量と消費量のバランスを取るために、需要調達計画と発電販売計画の提出や、需給差分の調整も必要となります。
一般的な電力供給との違い
一般的な電力供給は、電力会社から電力を購入して使用します。一方、自己託送では、自社で発電した電力を自社で消費する点が大きく異なります。
また、電力会社からの供給で発生する再エネ賦課金や燃料調整費などの料金は、自己託送では発生しません。
さらに、自己託送では電力の調達を自社でコントロールできるため、電力の安定供給やコスト管理がしやすくなります。しかし、その反面、送配電網の使用料や設備の維持管理費用などが発生する点は注意が必要です。

自己託送の料金体系

自己託送を導入するうえで最も気になるのが「費用面」ではないでしょうか。
導入や維持にかかるコストを理解し、費用対効果をシミュレーションすることが重要です。
自己託送にかかる初期費用
自己託送の初期費用には、主に発電設備の設置費用と系統接続のための設備費用があります。
例えば、太陽光発電設備の設置費用は、設備の種類や規模、設置条件により異なりますが、5kW程度までで約100万円〜150万円程度が相場とされています。
企業規模によりますが、数百kWの設備を導入する場合、数千万円の投資が必要になることもあります。最新の市場価格や公的機関の統計データを参照し、正確な見積もりを取得することが重要です。
また、送配電網に電力を送るための接続工事費用も必要です。この費用には、送電線や変電設備の建設費用、接続申請に伴う手続き費用などが含まれ、場合によっては数百万円から数千万円になることもあります。
具体的な費用は地域や設備仕様、送電距離によって異なるため、事例や専門家の意見を参考に詳細な検討が必要です。さらに、計測装置や遠隔監視システムの導入費用も考慮する必要があります。
運用コストと維持費
運用コストは、送配電網の使用料である託送料金が代表的です。託送料金は電力会社や契約内容によって異なりますが、1kWhあたり十円程度が一般的です。
また、発電設備の維持管理費用も発生します。維持管理費用は設備の種類や運用状況によって異なります。設備の点検や修理、消耗品の交換などが必要となり、野立てであれば草刈りの費用も見込んでおくことが重要です。
維持管理費用の具体的な算出には、専門家の見解や実績データを参考にしましょう。
さらに、需給バランスを維持するためのインバランス料金も考慮が必要です。計画した発電量と実際の消費量に差異が生じた場合、その差分について料金が発生します。これを抑制するためには、精度の高い需給計画の策定や運用体制の整備が求められます。
料金シミュレーションと費用対効果
自己託送の導入を検討する際、初期費用や運用コストに対して、どれだけの電気料金削減効果が見込めるかをシミュレーションすることが重要です。
これにより、投資回収期間や長期的なコスト削減効果を予測できます。
シミュレーションでは、発電設備の発電量、消費地点の電力需要、託送料金、設備の維持費用、インバランス料金などを考慮します。
これらの要素を詳細に分析し、費用対効果を明確にすることで、導入判断の材料とすることができます。

自己託送のメリットとデメリット

自己託送は、上手に活用すれば大きな経済的メリットをもたらします。しかし一方で、複雑な手続きや需給バランスの管理に手間がかかるなど、デメリットも存在します。
メリット:電気料金の削減が可能
自己託送により自社で発電した電力を使用することで、電力会社からの購入電力量を減らすことができます。これにより、電気料金の大幅な削減が期待できます。
また、自己託送では再エネ賦課金や燃料調整費といった付加料金の負担もありません。
さらに、電力価格の変動リスクを抑えることができるため、長期的なコスト安定化にも寄与します。電力の自給率が上がることで、エネルギーコストの削減と経営効率の向上が図れるでしょう。
デメリット:法規制や手続きが複雑
一方で、自己託送の導入に大きな費用がかかることのほかに、複雑な法規制や手続きが伴うというデメリットがあります。
自己託送をおこなうためには、電気事業法や関連法規に基づく各種手続きが必要です。一般送配電事業者との契約や発電設備の設置許可など、多くの手続きを適切におこなわなければなりません。需給計画の提出と、実際の受給値の報告も必要です。
また、法規制の改正や電力制度の変更に対応するため、最新の情報を常に把握し、適切な対応が求められます。これらの手続きや規制対応には専門的な知識が必要であり、時間や労力がかかる点がデメリットといえます。

まとめ
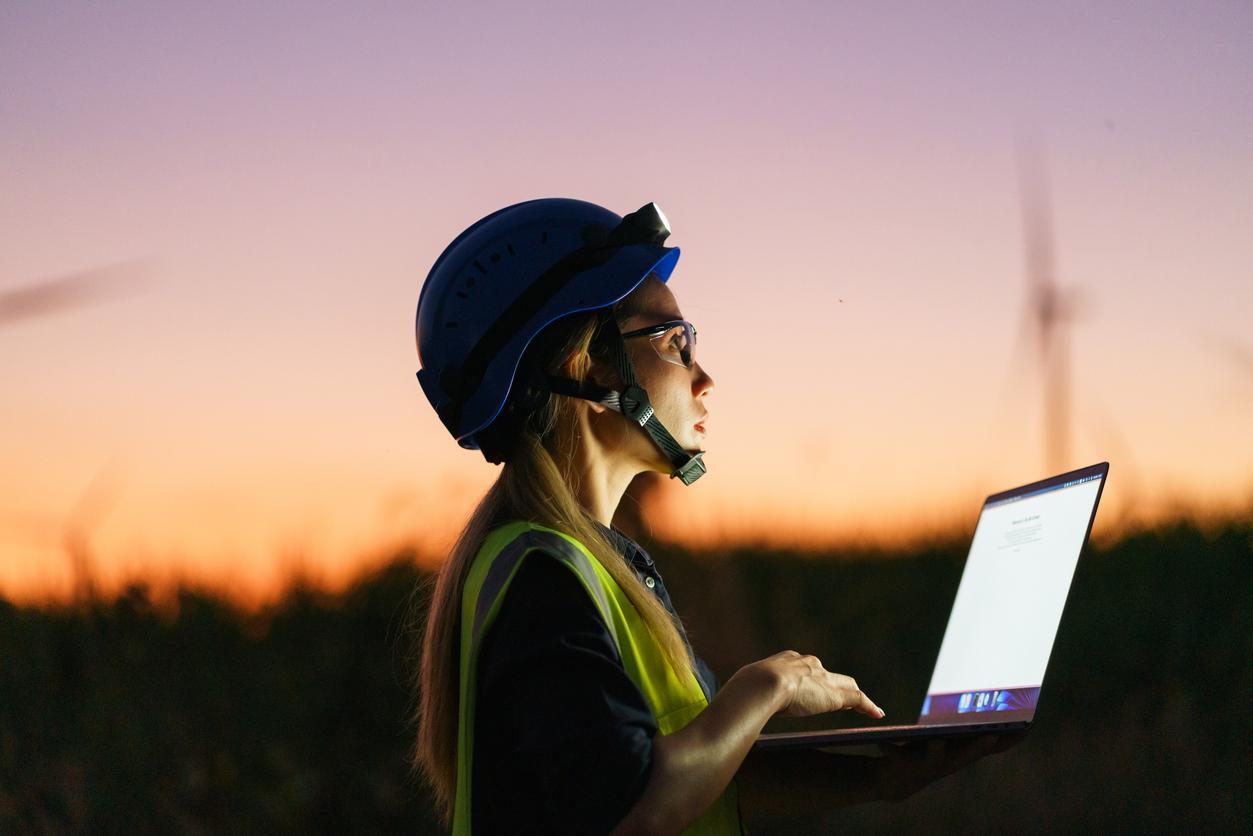
自己託送は、自社で発電した電力を活用し、電気料金の削減や脱炭素化を推進する有効な手段です。
自己託送を導入することで、電力コストの削減や環境負荷の低減といったメリットが期待できます。
しかし、一方で法規制や手続きの複雑さ、初期費用や運用コストの負担といった課題も存在します。導入を検討する際には、これらのメリットとデメリットを比較し、費用対効果をしっかりと分析することが重要です。
エコまるでは、産業用太陽光発電や自己託送事業のサポートをおこなっています。ご相談からアフターフォローまで安心してお任せください。まずは資料請求・お見積もりから!