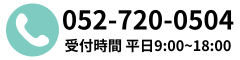近年、エネルギーの効率的な利用や環境への配慮が求められる中、「ZEH」という言葉を耳にする機会が増えています。
このコラムは、省エネ住宅の導入を検討している方が抱える疑問を解消し、ZEHについての理解を深めていただくために、ZEHの基本概念や仕組み、基準を満たすための技術や設備について詳しく解説します。
🌿 省エネ診断
5つの質問で、あなたに最適な
省エネ対策をオススメします!
診断結果
📚 関連記事をチェック
ZEHの基本概念と仕組み

まず、ZEHとは何か、その基本的な概念と仕組みについて理解しましょう。
ZEHは何の略?読み方は?意味と目的
ZEHとは、Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の略称で、「ゼッチ」と読みます。その名の通り、住宅で使用するエネルギー量と自ら生み出すエネルギー量を合算し、年間のエネルギー収支をゼロにすることを目指しています。
環境負荷の低減や光熱費の削減を実現することが目的です。エコと節約を両立したい方にはおすすめの仕組みと言えるでしょう。

ZEHの仕組み
ZEHの仕組みは、大きく分けて「断熱」「省エネ」「創エネ」の3つの要素から成り立っています。
「断熱」では、高断熱・高気密な住宅設計によって、外気温の影響を最小限に抑えます。
「省エネ」では、省エネ設備の導入によって、エネルギー消費量を抑えます。
「創エネ」では、太陽光発電などの再生可能エネルギーを活用して、自宅でエネルギーを生み出します。これら3つの要素を組み合わせることで、エネルギーの自給自足を目指すのです。
ZEHがエネルギー収支ゼロを実現する仕組み
エネルギーの収支ゼロを実現するためには、以下のポイントが重要です。
まず、高断熱・高気密の住宅によって冷暖房に使用するエネルギーを削減します。次に、太陽光発電システムなどの創エネ設備を導入します。するとエネルギーの消費量が減り、自家発電したエネルギーで生活が事足りるため、エネルギー収支がゼロになるのです。
ただし、ZEHにはさまざまな区分(ZEH、Nearly ZEH、ZEH Oriented、ZEH+など)があり、それぞれで基準が異なるため、詳細は専門家に確認することをおすすめします。
ZEHについてお悩みのことがありましたら、エコまるまでご相談ください!

従来住宅とZEHの違い
従来の住宅とZEHの大きな違いは、エネルギーの使用と生産に対する考え方にあります。従来の住宅は、外部からエネルギーを購入して使用するのが一般的でした。
しかし、ZEHでは、断熱性能の向上と省エネ設備の導入によりエネルギー消費を抑え、さらに創エネ設備でエネルギーを自給自足することを目指しているのです。
ZEHの推進は、環境への負荷を減らし、長期的な光熱費の削減や将来的な資産価値の向上も期待できます。
また、ZEH住宅は、省エネ性能を評価するBELS(建築物省エネルギー性能表示制度)において高評価を得られるため、資産価値が高まる可能性もあるのです。

ZEHの種類

ZEHは、国の政策としても推進されており、さまざまなタイプが定義されています。ここでは、ZEHの代表的な5つの種類についてわかりやすく解説します。
ZEH(ゼッチ)
ZEHとは、「住宅の断熱性を高め、エネルギー効率のよい設備を導入し、太陽光発電などでエネルギーを創出することで、年間の一次エネルギー消費量の収支をおおむねゼロにする住宅」のことです。
基本的なZEHの要件は以下の通りです。
- 高断熱仕様(外皮性能基準をクリア)
- 高効率な設備(照明・給湯・冷暖房など)
- 太陽光発電などの再生可能エネルギーシステムを導入
- 「省エネ量 + 創エネ量 - 消費エネルギー ≒ 0」
もっともスタンダードなZEHの形で、補助金の対象にもなります。
ZEH+(ゼッチプラス)
ZEH+は、ZEHの性能をさらに高めた上位グレードの住宅です。単にエネルギー収支をゼロにするだけでなく、快適性や安全性、災害時の備えなどを強化した住宅を指します。
主な追加要件は以下の通りです。
- より高い断熱性能(ZEHよりもさらに厳しい基準)
- 蓄電池やV2Hなどの高度なエネルギーマネジメント
- 電気自動車との連携や、万が一の停電対策が可能
将来的なスマートハウス化を見据えた住宅として注目されています。
ZEH Oriented(ゼッチ・オリエンテッド)
ZEH Orientedは、都市部の狭小地や集合住宅など、太陽光発電が設置できない環境でもZEHの考え方を導入する住宅です。
特徴としては以下のような点があります。
- 創エネ設備(太陽光発電)の設置は不要
- 高断熱・高効率な省エネ設備は必須
- 地域の気候や敷地条件に応じた対応
ZEHの「創エネなしバージョン」とも言える存在で、都市部の制約を受ける住宅に現実的な選択肢を提供します。
Nearly ZEH(ニアリーゼッチ)
Nearly ZEHは、ほぼZEHに近い性能を持つ住宅を指します。エネルギー収支が完全にゼロではないものの、目標の75%以上を削減できている住宅が該当します。
特徴は以下のとおりです。
- ZEH基準に近い高断熱・省エネ設備を採用
- 太陽光発電などで一部のエネルギーを創出
- 補助金の対象となる場合あり
土地や建物の制約で完全なZEHを実現できない場合でも、Nearly ZEHなら比較的導入しやすくなります。
Nearly ZEH+(ニアリーゼッチプラス)
Nearly ZEH+は、Nearly ZEHの性能に加えて、ZEH+と同等の先進的設備を一部導入した住宅です。エネルギー収支の90%以上を削減しつつ、蓄電やエネルギーマネジメント機能を備えているのが特徴です。
特徴は以下のとおりです。
- Nearly ZEHの基準をクリア
- 蓄電池、HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)などを搭載
- 災害時のレジリエンス向上にも貢献
Nearly ZEHにより高い機能性と安心をプラスした、ハイグレードな仕様です。
ZEHのメリット
ZEHは、環境への配慮はもちろん、家計や防災、資産価値といった観点からも、多くのメリットがあります。ここでは、特に代表的な3つのメリットについて詳しく解説します。
光熱費(電気代)を削減できる
ZEHの大きな魅力のひとつが、電気代などの光熱費を大幅に削減できることです。
ZEHでは、高断熱な建物と省エネ性能の高い設備を組み合わせることで、エネルギー消費を大きく抑えます。さらに、太陽光発電などの再生可能エネルギーを活用することで、家庭で使う電力の多くを自給自足できるようになります。
また、余った電力は電力会社に売ることもできるため、実質的に光熱費がゼロ、あるいはプラス収支になるケースもあります。
時間帯別料金プランを契約して電気代が安い深夜に電力を使用するよう工夫したり、太陽光発電と蓄電池を併用することで昼夜問わず電力の自家消費が可能になるなど、ZEHは家計にやさしい住宅と言えるでしょう。
停電など災害時も電気を使えて安心
近年、地震や台風などによる長時間の停電が全国各地で発生しています。そんな時にも、ZEHは自立型の住宅として心強い存在になります。
太陽光発電と蓄電池を備えたZEHであれば、停電時でも昼間は太陽光、夜間は蓄電池から電力を供給することが可能です。冷蔵庫やスマートフォンの充電、最低限の照明や情報収集の手段が確保できるため、災害時の不安やストレスを大きく軽減できます。
災害に備えるという意味でも、ZEH住宅は高く評価されています。

資産価値が高くなる
ZEHは省エネ性能が高く、環境にやさしい住宅として、将来的にも資産価値を維持しやすいとされています。住宅の断熱性能やエネルギー性能が「見える化」されることで、購入希望者や査定者からの評価が高くなりやすいのです。
2025年4月以降、新築住宅に省エネ基準への適合が義務づけられており、ZEH基準に適合した住宅は将来の法規制にも対応済みとみなされ、住宅市場での優位性が高まる可能性があります。
省エネ性能の高さが「住宅性能表示」などで証明でき、今後の省エネ・脱炭素社会に対応した住まいとして認められることや、国や自治体の補助金制度が使えることも魅力のひとつです。
ZEHは「住み心地の良さ」と「将来的な資産性」を両立した、時代に合った住宅スタイルと言えるでしょう。
ZEHのデメリット
ZEHは、省エネ性能や災害時の備えなど多くのメリットがありますが、一方で事前に知っておくべきデメリットも存在します。ここでは、ZEH導入の際に注意すべき代表的なポイントを3つに分けて解説します。
初期費用が高い
ZEH住宅は、高性能な断熱材や省エネ設備、太陽光発電システム、蓄電池などの先進的な機器を導入する必要があるため、一般的な住宅より初期費用が高くなりがちです。
具体的には、通常の注文住宅よりも数百万円程度高くなるケースもあり、導入にあたっては十分な資金計画が求められます。
費用がかさむ主な要因としては、高断熱仕様の建材、太陽光発電パネル・パワーコンディショナ、蓄電池やHEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)などが必要になることがあげられます。ただし、国や自治体の補助金制度を活用することで費用を軽減できる場合もあるため、導入前には最新の支援制度を調べておくことが重要です。

メンテナンスコストがかかる
ZEH住宅では、導入する設備が増える分、定期的な点検や部品交換といったメンテナンス費用も発生します。想定されるメンテナンスは、太陽光パネルの点検・清掃、パワーコンディショナの交換、蓄電池の劣化による交換などです。
これらの費用を見越して、導入後のランニングコストもしっかり計画に含めておくことが大切です。
天候や環境によって発電量が左右される
ZEHの大きな柱である太陽光発電は、天候や立地条件の影響を大きく受けます。曇りや雨の日が続くと発電量が落ち込み、自家消費に回せる電力が減るため、その分の電力を購入しなければならず、電気代が高くなることもあります。
また、隣接する建物の影や屋根の方角・傾斜角などによっても、発電効率が左右されます。
ZEHの性能を最大限に活かすには、土地選びや屋根の設計段階から工夫が必要です。また、発電量の波をカバーするために蓄電池を併用するのも有効な対策といえるでしょう。
ZEH基準を満たすための技術と設備
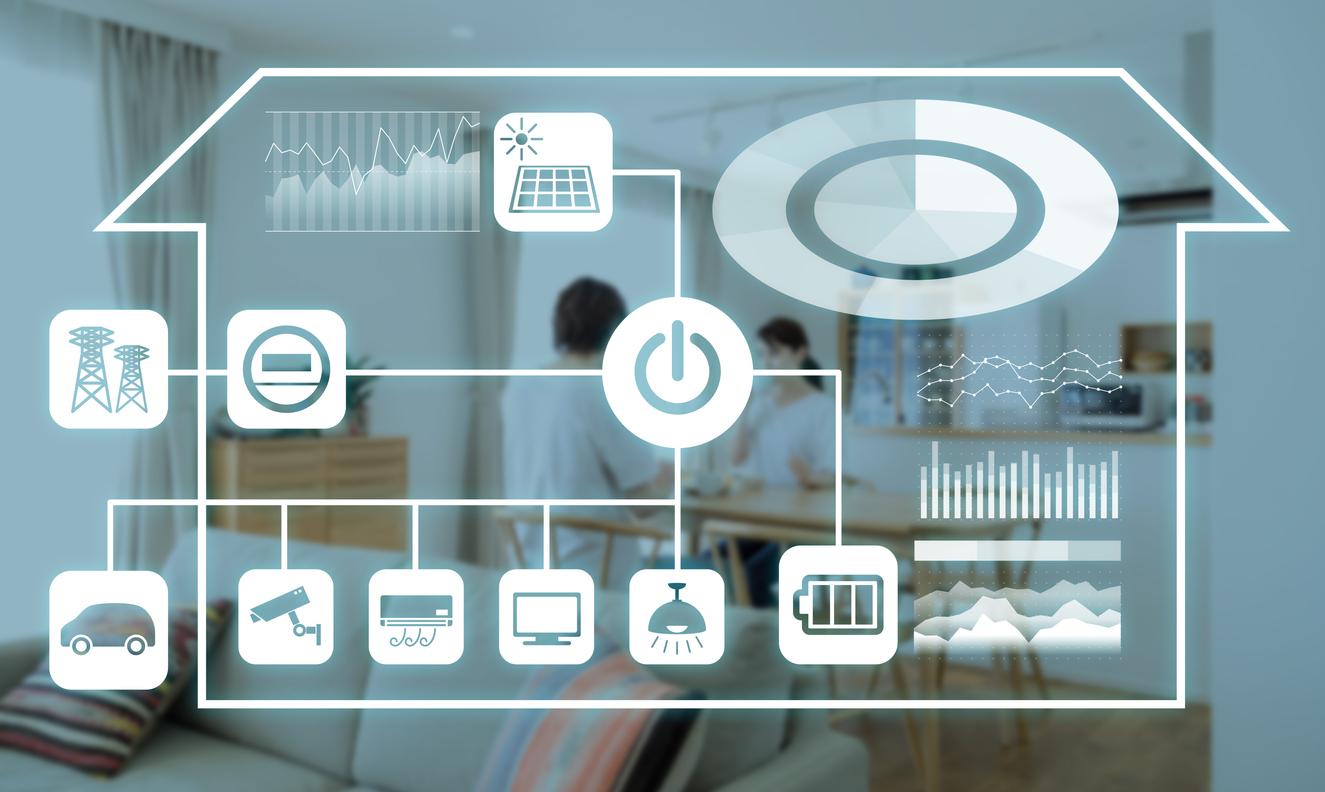
ZEHの基準を達成するためには、さまざまな技術と設備の導入が必要です。ここでは、その具体的な方法について解説します。
高断熱・高気密住宅の設計
高断熱・高気密な住宅を設計することは、ZEHの基本です。
断熱材の厚みを増やし、気密性の高い建材を使用することで、外気からの影響を最小限に抑えます。冬は暖かく、夏は涼しい快適な室内環境を維持できるでしょう。
また、冷暖房にかかるエネルギー消費も大幅に削減できます。住みやすさと省エネの両方を実現するうえで、高断熱・高気密は欠かせない要素なのです。
省エネ機器の(LED照明、高効率エアコンなど)
省エネ性能の高い機器を導入することも重要です。
具体的には、消費電力の少ないLED照明や、高効率のエアコン、エコキュート(自然冷媒ヒートポンプ給湯機)などの給湯器を採用することになります。
これらの機器は、従来品と比べてエネルギー消費が少なく、長期的な光熱費の削減につながります。

創エネ設備(太陽光発電、蓄電池)
自宅でエネルギーを生み出すためには、創エネ設備の導入が不可欠です。
太陽光発電システムを設置することで日中に電力を生み出し、家庭内で使用できるようになります。
使い切れなかった電気は電力会社に売却(売電)することになりますが、売電価格は低下傾向にある点を踏まえておく必要があるでしょう。現在では売電収入よりも自家消費を重視する流れに変わりつつあります。
参考:資源エネルギー庁「買取価格・期間等(2025年度以降)」
参考:資源エネルギー庁「買取価格・期間等(2012年度~2024年度)」
自家消費では蓄電池の併用が欠かせません。蓄電池があれば、昼間に使用しきれなかった電気を夜間や停電時にも活用できます。


ZEHは補助金を利用できる

ZEH住宅には、さまざまな機器や高性能な設計が必要になるため、従来の住宅よりも初期費用が高くなりがちです。しかし、このコストは補助金を活用することで抑えられます。
国や自治体からの補助金制度があり、条件を満たすことで補助金を受け取ることができます。ただし、補助金申請では制度に定められた要件を厳格に守る必要があります。間取りや設備の大幅な変更は難しくなる点に注意してください。
ZEHの補助金については、こちらのコラムで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。


まとめ

ZEHとは、省エネと創エネを組み合わせて、年間のエネルギー収支を概ねゼロにする住宅を指します。高断熱・高気密な住宅設計や、省エネ機器、太陽光発電システムなどの導入によって実現可能です。
ZEH住宅は光熱費の削減だけでなく、快適な住環境、環境負荷の低減、健康面でのメリット、将来的な資産価値の向上など多くのメリットがあります。
住宅の購入や建築を検討されている方は、ZEH住宅という選択肢をぜひ考えてみてください。未来の暮らしを見据え、より良い住まいを実現しましょう。ZEHが気になる方は、エコまるまでご相談ください!